退職代行 新卒 入社1ヶ月 辞めたいという検索をしているあなたは、おそらく今の職場に強い違和感を感じ、「やっぱり辞めたい」と思っているのではないでしょうか。新卒採用で入社したばかりでも、思っていた業務とのギャップや人間関係など、辞めたくなる理由は人それぞれです。
実際には、早期退職をする新卒の割合も決して少なくなく、入社後1ヶ月で辞めたいのですが、辞められますか?や、即日辞められますか?といった悩みを持つ方は年々増えています。一方で「おかしいと思われないか」など、社会的な目線を気にして退職をためらう人も多いのが現状です。
さらに、ベンチャー 半年 退職や2社目 すぐ辞めるといったケースも一般的になってきており、働き方の選択肢は以前より柔軟になっています。この記事では、退職代行を活用してスムーズに退職するためのポイントや、退職後その後のキャリアについても詳しく解説していきます。
記事に関しては厚生労働省ホームペーを参考にしています。
引用元 総合労働相談窓口
引用元 アディーレ法律事務所
記事ポイント
- 新卒で入社1ヶ月でも退職は法律上可能であること
- 退職代行を使えば実質的に即日退職ができる可能性もある
- 短期離職のリスクとその後の転職活動の進め方
- ベンチャー勤務や早期退職に対する正しい向き合い方
【お知らせ】
当ブログで紹介している「退職代行モームリ」は、現在トラブルによりサービスを一時停止しているとのことです。
記事内の情報と異なる場合がございますので、ご注意ください。
新卒1ヶ月で退職代行はアリ?

- 入社後1ヶ月で辞めたいのですが、辞められますか?
- 即日辞められますか?
- 新卒採用でも退職は自由?
- やっぱり辞めたいと思ったら
- ベンチャー 半年 退職のリスク
入社後1ヶ月で辞めたいのですが、辞められますか?
結論から言うと、入社1ヶ月で退職することは可能性な場合もあります。これは、規定によって、雇用期間が定められていない正社員であれば、いつでも退職の意思を示すことができると明記されているためです。たとえ入社したばかりであっても、新卒であっても、正社員として雇用されているのであれば、退職の自由は労働者に保障されています。
さらに、退職の申し出から2週間が経過すれば、法的に雇用契約は終了するため、会社の同意がなくても手続きは進めることが可能です。例えば、職場の人間関係が思っていた以上にストレスフルだったり、業務内容が自分に合わないと強く感じた場合などは、退職を検討する理由として十分といえるでしょう。
無理に続けて精神的・肉体的に不調をきたす前に、早めの判断で自分自身を守る行動をとることも大切です。退職することが「逃げ」と思われがちですが、むしろ長期的に見れば、健康を守る賢い選択である場合も少なくありません。
参考サイト 労働弁護士ガイド
即日辞められますか?
基本的に、法律上では退職の意思を伝えた日から原則2週間の猶予期間が必要とされています。しかし、退職代行サービスを活用すれば、その日から会社に出社せずに退職手続きを進めることができるため、実際の感覚としては「即日退職」が可能な場合もあります。
例えば、退職代行業者が本人に代わって退職の意思を会社に伝えた時点で、実務上はその日をもって業務が終了する場合も少なくありません。さらに、会社側がその申し出を円滑に受け入れ、手続きを迅速に進める体制が整っている場合には、翌日以降の出社が不要となり、精神的な負担も軽減されます。
このような背景から、制度上は即日退職とは言い切れないものの、実際には「その日をもって職場から離れられる」形で退職が進むため、多くの人にとって即日退職と同等に感じられるのです。
こちらからから↓

新卒採用でも退職は自由?
新卒採用であっても、退職の自由は法的にきちんと守られています。実際、労働者の権利として、雇用期間の定めがない場合にはいつでも退職の意思を示すことができると、民法で明記されています。現在の私は、かつて「せっかく入ったばかりなのに辞めるの?」と強く引き留められた経験がありますが、そのときも法的には全く問題はありませんでした。
また、上司や人事担当者が不満そうな態度を取ることがあっても、退職は個人の自由であり、誰かに許可をもらうものではありません。むしろ、自分の心と体に不調が出始めているのに無理をして働き続けることのほうが、将来的に大きな問題へとつながる可能性があります。
例えば、精神的な思いや過労が原因で病院に通うようになったり、休職を余儀なくされたりするケースも珍しくありません。退職は自己都合で決めることができる大切な権利であり、自分の未来や健康を守るための選択肢として、遠慮する必要はないのです。

やっぱり辞めたいと思ったら
やっぱり辞めたいと感じたときは、無理をせず、真剣に向き合うことが大切です。
他にも、先輩社員との関係がうまくいかなかったり、上司からのプレッシャーが強すぎて毎日憂うつになるようであれば、それは自分自身の限界を知らせるサインかもしれません。無理しても自然に解消されることは少なく、むしろ放置することで状況が変わることがあるように思います。
こうした背景を踏まえ、まずは自分が何にストレスを感じているのかを明確にすることから始めましょう。そのうえで、信頼できる人に相談したり、転職という選択肢を含めて行動に移す準備を進めていくことが、より健全な未来への第一歩となります。
ベンチャー 半年 退職のリスク
ベンチャー企業で半年以内に退職することには、確かにキャリア上の不安が伴います。特に、履歴書に短期間の離職歴が記載されることで、次の転職活動においてマイナスに働くのではないかと心配になる人も多いでしょう。また、「すぐ辞めた人」として評価が下がるのではと感じるかもしれません。
しかし、それ以上に心身の健康を損なうような状況に置かれているのであれば、その職場にとどまること自体がより深刻になると思います。特にベンチャー企業では、急成長を目指す過程で人手不足が慢性化していたり、長時間労働や休日出勤が常態化していることも珍しくありません。さらに、組織体制が未整備なために業務が属人化しており、サポート体制も整っていないケースも多いように感じます。
例えば、上司による理不尽なこと、1日12時間以上の労働が連日続くような状況で、「このままで大丈夫だろうか」と疑問を感じながら働いているのであれば、それはすでに限界が近づいているサインかもしれません。そのような状態で無理を重ねても、心身ともに疲弊し、結果的に長期離脱せざるを得なくなる状況になると思います。
このため、半年という期間にこだわりすぎることなく、状況を冷静に見極めて必要なら早めに方向転換するという判断は、決して後ろ向きな選択ではなく、むしろ前向きで自分の未来を大切にする行動といえるのです。
こちらからから↓

退職代行 新卒 入社1ヶ月 辞めたい人へ

- その後の転職活動はどうなる?
- 2社目 すぐ辞めるとどうなる?
- おかしいと思われる?
- 割合で見る新卒早期退職
- 退職の伝え方と注意点
- 後悔しない判断のために
その後の転職活動はどうなる?
退職後の転職活動について不安に思う方も多いかもしれません。特に新卒で入社1ヶ月という短期間での退職となると、次の職場でネガティブに受け取られるのではないかと心配になるのは自然な感情です。しかし、実際には短期離職であっても、きちんとした理由をもって誠実に説明すれば理解されるケースがほとんどです。
例えば、「体調に支障をきたすほど労働環境が合わなかったため、早期に見切りをつけて別の道を模索することにした」という説明は、誠実さと自己判断力を示す例として評価されることがあります。企業側も、長期的に働ける人材を求めているため、ミスマッチのまま働き続けるよりも、早い段階で問題に気づいて対処した姿勢を前向きにとらえる傾向があります。
加えて、退職後の期間をどう過ごしていたかも重要です。例えば、資格の勉強をしたり、自己分析を深めたりしていたという事実があれば、それも立派なアピール材料になります。短期離職は決して致命的なハンデではなく、その後の行動によっていくらでもプラスに転じることができるのです。
こちらからから↓
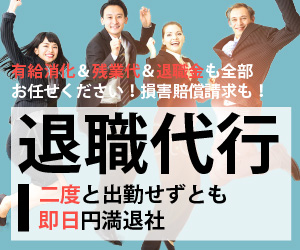
2社目 すぐ辞めるとどうなる?
2社目も早期に辞めてしまうと、「すぐ辞める人」という印象を採用担当者に与えてしまう可能性が高まります。その結果、企業側からは「またすぐに辞めてしまうのではないか」「長期的な戦力として見込みが薄いのでは」といった不利な評価につながるリスクがあります。
これを避けるためには、次の職場選びをより慎重かつ計画的に行うことが不可欠です。まず、自分が何に違和感を感じていたのか、どんな職場環境が合わなかったのかを自己分析によって明確にすることが第一歩です。次に、その結果を踏まえて、自分に合った職場像を具体的にイメージし、それに見合う企業を探す必要があります。
例えば、企業の口コミサイトやSNS、業界掲示板などで、社内の雰囲気や働き方に関するリアルな情報を集めるのは有効な方法です。さらに、応募先の面接時には遠慮せずに、「具体的な業務内容」や「1日の流れ」「評価制度」「残業時間の実態」などを詳しく確認することが重要です。
また、企業説明会や社員とのカジュアル面談などを活用することで、実際の働き方や社風に対する理解を深めることもできます。このように事前の情報収集と自己理解を徹底することで、2社目の早期離職を防ぎ、長く安心して働ける職場に出会える可能性が高まるでしょう。

おかしいと思われる?
「入社1ヶ月で辞めるなんておかしいと思われないか」と不安になるのは自然なことです。特に周囲からの期待や「新卒は最低でも3年は続けるべき」といった社会的な常識に縛られていると、そのような不安はさらに大きくなるものです。しかし、実際には多くの人が同じような悩みを抱えており、早期に退職する選択をした人も決して少なくありません。
また、現代では働き方に対する価値観も多様化しており、「合わない場所からは早めに離れるのが正解」という考え方も一般的になってきています。企業にとっても、無理をして働き続けて成果が出ない社員よりも、自分に合った環境で本領を発揮できる人材の方が価値があるのです。
つまり、辞めること自体が非常識だと決めつける必要は全くありません。むしろ、自分自身の心と体の状態を最優先に考えた行動は尊重されるべきです。周囲の意見に流されるのではなく、自分の気持ちや価値観を大切にしながら決断することが、長い人生を見据えた上でとても大切な姿勢だといえるでしょう。
参考サイト 労働弁護士ガイド
割合で見る新卒早期退職
実際、新卒の早期退職者は一定数存在します。例えば、厚生労働省の調査によると、3年以内に約3割以上の新卒が離職しているという統計が報告されています。これは、新卒の約3人に1人が、入社後3年以内に退職していることを意味しており、決して珍しいことではありません。
この数字を見ればわかる通り、早期退職というのは社会全体で広く見られる現象であり、特別視すべきものではないのです。もちろん、早期退職をネガティブに受け取る人も中にはいますが、近年では「自分に合わない職場から早く離れるのは健全な選択」という価値観も浸透しつつあります。
自分自身だけが例外的な存在であるとか、弱い人間だと感じる必要はありません。むしろ、自分にとって良くない環境から距離を取る勇気を持つことこそが、健全な自己管理の一つといえます。自分のキャリアは自分で築くものであり、早期退職をきっかけにして、自分に合った道を模索していくことが何よりも大切です。
こちらからから↓
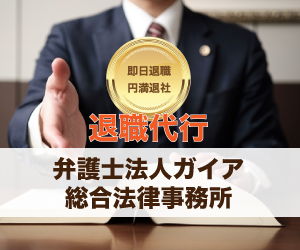
退職の伝え方と注意点
退職を伝える際には、感情的にならず冷静に伝えることがとても大切です。突然の退職の申し出に対して、相手も驚いたり感情的になる可能性があるため、落ち着いた態度で丁寧に伝えることが、円満退職のための第一歩となります。私であれば、事前に退職理由や伝える内容を紙にまとめ、あらかじめ整理しておくことで混乱を避けます。
具体的には、退職の意思を伝える場面では「一身上の都合により退職させていただきたいと思っております」といった定型的で穏やかな表現を用いると、相手に不快感を与えにくくなります。さらに、文書として退職届を用意しておくと、手続きがスムーズに進みますし、誠意も伝わりやすくなります。
また、会社から支給されている備品の返却や、業務の引き継ぎなども重要なポイントです。これらを怠ると、最後に印象を悪くしてしまう恐れがあります。たとえ職場環境に不満があったとしても、社会人としてのマナーを守ることは大切です。しっかりと準備し、相手の立場にも配慮した対応を心がけましょう。
こちらからから↓

後悔しない判断のために
退職を決断する前に、自分の気持ちとしっかり向き合うことがとても重要です。感情の高ぶりや一時的感情の中で決断を下すと、後から「もう少し冷静に考えておけばよかった」と後悔してしまうことが少なくありません。そのため、まずは自分の気持ちを丁寧に見つめ直す時間を持つことをおすすめします。
このように考えると、勢いで辞めてしまって後悔するリスクを大幅に減らすことができます。例えば、自分が何に不満を感じているのか、何が原因になっているのかを紙に書き出してみるのは有効な方法です。それにより、漠然としていた不安が可視化され、頭の中が整理されやすくなります。
また、信頼できる友人や家族、もしくはキャリアカウンセラーのような第三者に話を聞いてもらうことで、自分では気づかなかった視点に触れることもあります。こうしてさまざまな角度から状況を見つめ直すことで、より納得のいく判断ができるようになります。
最終的に退職を選ぶ場合でも、「ちゃんと考えて決めた」と思えるプロセスを経ることで、後悔や迷いはかなり軽減されるでしょう。
退職代行 新卒 入社1ヶ月 辞めたい人が知っておくべきこと

記事をまとめています。
- 新卒でも入社1ヶ月で退職は法律上可能
- 正社員であれば退職の自由が保障されている
- 退職代行を使えば実質的に即日退職も可能な場合もある
- 新卒採用での退職も法律的に問題はない
- 辞めたい気持ちは無視せず原因を明確にするべき
- 職場の雰囲気が合わないなら早期判断も大切
- ベンチャーでの長時間労働は早期退職の理由になりうる
- 短期離職でも転職活動で誠実に説明すれば理解される
- 2社連続で早期退職すると評価が下がると思われる事がある
- 早期退職はおかしいと思われる不安は社会的プレッシャーによるもの
- 実際に新卒の約3割が3年以内に退職している
- 辞める際には冷静に穏やかに意思を伝えることが重要
- 退職後に何をするか明確にしておくと次に進みやすい
- 後悔しないために気持ちを整理して決断する必要がある
- 退職代行の法的根拠の注意点「交渉は弁護士・労働組合に限られます」
カケコム即日退職参考サイト
関連記事
退職代行モームリ使ってみた!即日対応の流れと依頼料の詳細
退職代行ニコイチクレームの実態と評判を徹底解説
退職代行モームリクチコミ検証|利用者の本音と注意点
退職代行いつから使えるか完全ガイド【即日対応も解説】










コメント